サーバント・リーダーシップとは何でしょうか?パワハラなどが話題になるにつれて、サーバント・リーダーシップという言葉を聞くことも多くなってきました。しかし、それがどういうものなのか、きちんとした説明を聞く機会はさほど多くありません。
この記事では、サーバント・リーダーシップについて、「支援的な関わり」と「影響力によるリーダーシップ」の2つの側面から説明します。
サーバント・リーダーシップとは?
まずはじめに、サーバント・リーダーシップを簡潔に定義しておきます。
サーバント・リーダーシップとは、支援的な関わりを提供することによって、主体的な行動を促す影響力を行使するリーダーシップである。
大きく2つの要素に分けて説明します。一つはサーバントとして支援的な関わりを提供すること、もう一つはリーダーとして主体的な行動を促す影響力を行使することです。
支援的な関わりを提供するサーバント
サーバント(servant)とは、しもべや召使いを意味します。相手のために仕え、役に立つ人のことです。サービスという言葉と同じ、serve(仕える、給仕する)という動詞に由来します。
支援的な関わり
サーバントとして相手のために仕えることの本質は、「与える」ことにあります。本来は自分のために使うものを、相手に利益、よいものをもたらすために差し出し、与えるということです。当然、自分は失い、相手が得ることになります。それを良しとして、犠牲を払うのが仕えることです。
具体的には、時間や労力、金銭、関心、知識などを、相手に提供することです。受ける相手は、自分だけでは得られなかったものを手にします。よい歩みが実現していく助けになるでしょう。
相手のために仕えること
同じ与える行為でも、相手のためではない動機でなされる場合もあります。例えば、品物を買って代金を支払うという行為は、相手にお金を与えています。でも、相手に仕えているのではありません。品物の対価を支払っているだけです。利益を受ける見返りに、自分のものを差し出すのは、与える行為とは言えません。
与えることは、「相手のために」という思いに基づきます。
- 相手の課題が解決するため
- 相手の目的が果たされるため
- 相手が困らないため
- 相手が喜び、満足するため
- 相手が成長するため
相手のためによいことを思い、そのために自分が払う犠牲を惜しまないことです。
相手のためと見せかけて、自分のために与えることも見受けられます。
- 与えることによって相手を操作する
- 与えることによって相手を安心させて騙す
- 与えることによって相手を間違った方向に導く
- 与えることによって相手を甘やかす
- 与えることによって相手を味方につける
こういったことは、与えて仕えることとは正反対です。
サーバントの自己認識
サーバントは、相手のために与え、仕えることを最大の使命だと考えています。自分が仕えることによって、相手に何がもたらされるのかを見通し、それを励みとし、できる精一杯の貢献をしようと努めます。
嫌々しているのではありません。強いられて仕方なくしているのでもありません。自分のすべき使命だと理解し、受け止めているのです。
サーバントは、自分の理想の姿について、ステージに立つスターであるべきだとは考えません。相手がスターとして舞台に立つことができるように支援する裏方スタッフこそが、サーバントの思い描く自己像です。自分の能力の高さ、素晴らしさを讃えられるよりは、自分の支えによって誰がどう活躍しているかによって讃えられることを望みます。
与えるために与えられているものがある
サーバントとして仕えるためには、まず与えるために与えられているものがあるという認識が重要になります。すべての人に、相手のために用いるようにと与えられているものがあります。自分の能力や状況、環境、経験、財産など様々なものです。
特別な能力や才能だけでなく
そう聞くと、特別な能力や才能などを思い浮かべることでしょう。「私は平凡な人間で、特に誇るようなものは何もない」という声が聞こえてきそうです。
しかし、与えられているものは、人より秀でた特別な才能や能力のことだけではありません。誰にでも与えられている時間や、誰にでもできる声かけ、ちょっとした手助けなども、与え、仕えるために用いられます。
例えば、ある人は時間が自由になり、相手のためにそれを割くことができるでしょう。ある人は気配りができ、必要に気がついてあげることが相手に対する支援になります。またある人は自分が経験したことをとおして、同じような歩みをしている人に助言を与えることができます。
相手のために、何もできない、ということはありません。何もかもすべてのことはできなくても、何かしらのことはできるものです。それを自覚し、喜んで差し出していくのがサーバントです。
一人一人がユニークな存在として
与えられているものを考えると、一人一人で違っていることが容易に理解できるでしょう。誰一人として、同じ能力、性格、気質、状況、経験、財産を有している人はいません。それぞれ、みな違います。サーバントは、自分に与えられているもので、自分にだからこそできるかたちで、相手のために関わります。
そのとき、他人と比較することは無意味です。あの人は何をどれだけしたか、自分はどれほどのことができたか、比べても仕方ありません。というのは、それぞれが与えられているものが違いますし、期待される関わり方も違うからです。
サーバントは、自分自身に与えられているものを自覚し、人との比較に悩まされることなく、相手のために自分の果たすべき分を果たして仕えます。
主体的な取り組みを促すリーダー
このようなサーバントは、リーダーとは程遠いと感じるでしょう。相手のためにと関わってばかりいたら、みんなが自由に振舞って収拾がつかないのではないか。組織の目標を達成することが難しいのではないか。部下の言いなりになるべきだというのか。そう考えるのは当然のことです。
サーバントがリーダーシップを発揮するとはどういうことか、詳しく見ていきましょう。
影響力によるリーダーシップ
サーバント・リーダーシップは、リーダーシップですので、部下の召使いになって使われることを意味しません。むしろ、相手に仕えることによって、共通の目的に向かっていくように影響を及ぼします。ふさわしい行動を促し、良い結果が出るように励まします。
対象的なのは支配型のリーダーです。立場や役職、年齢や経験の差などによって強制的な指導力をもっています。力や立場の差がある場合、それによって相手を動かすことは簡単です。命令、指示を出せば、そのとおりに行動するからです。
サーバント・リーダーは支援型のリーダーであり、その持つ力は影響力です。与え、仕え、支援的に関わることで、相手が動き出すことを促します。権力による命令や指示によってではありません。相手が自ら課題に取り組んでいくように影響を与えます。
このような関わりは、簡単ではありません。共通の目的が認識され、良い信頼関係が築かれ、相手が十分に尊重される中で、主体的な行動が生み出されていきます。このことをもう少し具体的に見ていきましょう。
同じ目的のために一人一人が主体的に
サーバントが行使するリーダーシップの一番重要なことは、相手に主体性をもたせることです。
主体性とは
主体性とは、以下のように理解できます。
- 他の誰かではなく、自分のすべきこととして受け止めている
- 何をどのようにすべきか、自分で見出し、取り組もうとしている
- 困難な状況であっても、自分として最大限の努力をしようとしている
- 取り組みの結果について自分が責任を負っていると自覚している
部下を指導する立場にある方ならば、自分の部下がこういう主体性を持っていたらどんなにすばらしいだろう、と思うことでしょう。サーバント・リーダーはこのような主体性を持たせるように関わります。
モチベーション3.0
人はどのようにして動機づけられ、主体性を持つようになるのか、今までも多くの研究がなされてきました。ダニエル・ピンクは著書「モチベーション3.0」で、以下のような動機づけの有効性を示しました。
- 最も原始的な動機づけは、危険の脅かしによるもの。うまくやらなければまずい、と怯えさせて頑張らせる
- 次のレベルの動機づけは、報酬によるもの。がんばればご褒美がある、と期待させて頑張らせる
- 最も有効な動機づけは、内面の喜びによるもの。使命に励むあなたはどんなにすばらしい人物か、と奨励する
- 動機づけは、外的なものよりも、状況に左右されることのない内発的なもののほうが有効である
- 内発的な動機づけは、個人の主体性を向上させ、より意欲的な取り組みとなる
共通の目的の提示、内発的動機づけ
モチベーション3.0を参考に、主体性を向上させる関わりについて考えてみましょう。
当事者の内発的動機づけのためには、大きな目的と自分自身の目的が重なり合うことを示すことが重要です。「この大きな目的を果たすためにはあなたの貢献が不可欠である」と伝えます。と同時に、「このことに貢献することはあなたの喜びとなり、成長につながる」とも伝えます。
滅私奉公のように、個人の歩みを犠牲にして全体の問題に取り組む必要はありません。個人の歩みにも、全体の取り組みにも、双方に益する歩みがあることを示します。そのことによって、相手は自分が関わることの意義を見出すことができます。
主体性をもたらす関わり
共通の大きな目的を確認した上で、サーバントがリーダーシップを発揮するために、具体的にいくつかの関わりがあります。
当事者意識をもたせる
サーバントはメンバーに対して、当事者意識を植え付けます。当事者意識というのは、自分はこのことについて責任を負っているという自覚です。
具体的には、権限の移譲を行います。何にどうやって取り組み、目的を果たすのか、その決定権をメンバーに持たせます。
もちろん、基本的な報告、連絡、相談は、今まで以上に行います。しかし、その目的は上に立つ者が決定し、指示するためではありません。現場にいるメンバーが自分自身で有効な決定をすることができるように支援するためのものです。
これによって、メンバーは自分がこの責任を負うのだ、という自覚を育てられていきます。
個の在り方を尊重する
権限を移譲するということは、必要以上に干渉したり、型にはめるような指示をしないことを意味しています。
つまり、それぞれの個の在り方を尊重することになります。一人一人のメンバーは、それぞれ違った経験を積み重ね、違った個性を持ち、違った状況の中にあり、違ったものの見方をします。
そのような個の在り方を型にはめてしまえば、良い持ち味を殺してしまうことになります。むしろ、その在り方を認められ、用い方を見出されると、どうでしょう。これによって、生き生きと自分の力を最大限に発揮することができるようになります。
短所を補い、長所を活かす
サーバントの関わりの真骨頂となるのは、相手の欠点、短所が見えたときです。支配型のリーダーにとって、欠点や短所は許され得ません。努力などでカバーし、リーダーの指示を完全に果たすことが求められます。しかし、サーバントのような支援型のリーダーは、短所や欠点があるからと言って、それを責め立てるようなことはしません。
というのは、相手に対する基本的な信頼を持っているからです。
- 誰も好んでミスをする人はいない
- 取り返しのつかない失敗などない
- 誰にも長所もあれば短所もある
- 誰もが精一杯に責任を果たそうとしている
- 適材適所で人材を活かすのはリーダーの仕事だ
そのような信頼に基づいて、相手のもっとも活かされる関わりを見出していきます。
あるべき姿の模範を示す
サーバント・リーダーの影響力は、自らの仕える姿勢を模範として示すことによって、最大限発揮されます。
人は成長するために、自分はどんな人物になりたいのか、という将来像を思い描きます。そのとき、あの人のようになりたい、という模範が必要です。サーバントリーダーは、その模範的な将来像となることが理想です。
たとえば支援的なリーダーの以下のような姿は、メンバーも同じようになりたい、と思わせるものでしょう。
- 自分に与えられている責任を果たしている
- 相手のことを十分に尊重し、関わっている
- 人を立場に関係なく、正当に評価している
- 敵が少なく、多くの人から信頼されている
- 人の手柄をとらず、誰に対しても謙遜である
このような模範に倣っていくことによって、リーダーとメンバーの関係だけでなく、メンバー同士の関係も良好なものとなり、共同体全体が力強く動き始めていきます。
サーバント・リーダーシップについて、大きく2つの面から説明しました。支援的な関わりをするサーバントが、主体的な行動を促すリーダーとして機能するとき、個が尊重され、生き生きとした取り組みが実現します。
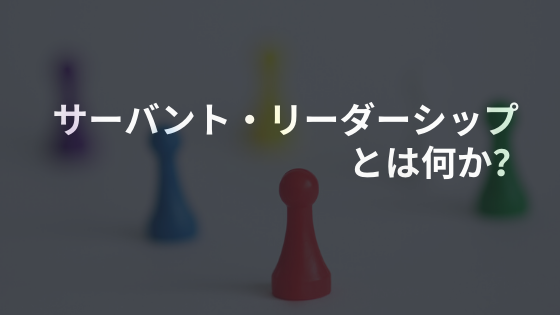
コメントを残す