普通のビジネスパーソンでも、コーチングの有用性が認められています。ミッション・ワーカーには、なおさらコーチングが必要です。今日の記事ではその理由と効果について、お伝えします。
孤軍奮闘するミッション・ワーカー
NHKの「プロフェッショナル」やTBSの「情熱大陸」などに、しばしばミッション・ワーカーが登場します。使命に励む人のドキュメンタリーは見どころが多く、ドキドキ、ハラハラの連続です。番組に登場するぐらいですから、最後には働きが実るのでしょう。ハッピーエンドを予感させます。
ところが、多くのミッション・ワーカーたちは、ハッピーエンドが約束されない中で、必死に取り組んでいます。それは、想像以上に危険なところ、挫折や燃え尽きと隣合わせです。
いくつか、典型的な状況を見てみましょう。
やることが次々と出てくる
ミッション・ワーカーの取り組みで、方法論が確立されていることはあまりありません。言い換えれば、どうするか考えなければいけない、新しい状況が次々に起こってくる、ということです。
ミッション・ワーカーは、そのような新しい場面に遭遇しながら、ひっきりなしに、やることをこなしていきます。見通しの立ちにくい、場当たり的な反応をせざるおえないことがしばしばです。
その繰り返しは、ミッション・ワーカーの体力、精神力を奪っていきます。一体いつまでこれを続けるのだろうか、という思いが湧いてきたら、燃え尽き寸前の黄色信号です。
協力者が少ないのでオーバーワーク
ミッション・ワーカーの現場では、いつも手が足りない状況です。幸いにも、使命を共有し、協力をしてくれる人もいます。しかし、与えられた課題に取り組もうと思えば、もっともっと人手を必要とします。潤沢な資金があれば、人を雇うこともできますが、それもままなりません。
結果として、ミッション・ワーカーはオーバーワークを強いられます。まず自分自身が限界まで取り組み、その背中を見たスタッフも同じ心意気で取り組む、そういう面が多々あります。
家族を顧みず、睡眠時間を削って使命に励むと言えば、かっこよく聞こえるかもしれません。ときには、そんな自分に酔うことだってあるでしょう。ただし、健全なことではありません。オーバーワークは、確実にミッション・ワーカーを消耗させます。
休むことに罪悪感がある
オーバーワークを免れない、もう一つの理由は、皮肉なことにその使命感にあります。
大切な使命であればあるほど、その先には助けを必要としている人たちがいます。ミッション・ワーカーは、具体的に関わっているので、そのひとたちの困難や痛みをいやというほど知っています。
誰かが助けの手を伸べなければいけない、自分がやらなければ彼(女)らは苦しいままだ… そう思えば、自分が休みをとって、余暇を楽しみ、リフレッシュするなんてことはできっこありません。
真剣であればあるほど、ミッション・ワーカーである自分のスイッチを切ることができないのです。
明るい展望を描きにくい
さらに、ミッション・ワーカーは、良い結果、報われる未来をイメージすることが困難です。もちろん、理想を描き、語ることはできます。しかし、目の前の現実と理想の間に、あまりにも大きなギャップがあります。夢物語は語れても、具体的な道筋を現実的に示すことが難しいのです。
目の前の大きな課題、自分たちのリソースの乏しさ、勝算のない取り組み、周囲からの評価… 考えれば考えるほど、取り組みを続けていく理由が乏しくなってしまいます。
理解されない孤独
ミッション・ワーカーの一番の悲しみは、孤独です。与えられた使命に基づいて、懸命に課題に取り組んでいるのに、周囲の理解が得られません。
いつまでそんなことをやっているのか、まわりに迷惑をかけっぱなしじゃないか、ただの身勝手だ… ときおり聞こえてくる声が、心にグサグサ刺さります。自分だって、そう思うときがあります。それを人から言われれば、ショックは大きいものです。ましてや、この人には協力してもらえると思っていた親しい人から言われてしまったら、立ち直れないほどのショックでしょう。
ミッション・ワーカーが、その崇高な使命に立つゆえに、どれほど過酷な状況を歩んでいるのか、理解していただけたでしょう。このままでは、ハッピーエンドのドキュメンタリー番組ではなく、悲しい結末がニュースで報道されることにさえ、なりかねません。
コーチングは将来につながる助け
そういうミッション・ワーカーに必要なのは、使命をよく理解し、気持ちを受け止め、力づけ、励ますコーチです。コーチは、ミッション・ワーカーに寄り添いながら、よりよい取り組みを見つける手助けをします。
コーチングは安易な助けではない
例として、道に迷ってしまった人をイメージしてみましょう。タクシーを拾えば、黙っていても(厳密に言うと黙っていてはダメで、行き先を告げると)目的地に連れて行ってくれます。コーチングはそういうものではありません。
道を聞けば、「真っすぐ行って、あの角を曲がって、3つ目の信号を…」と細かく教えてくれる人がいるでしょう。指示通りに行けば、たいてい目的地につくはずです。コーチングはそういうものでもありません。
コーチングは地図の見方も教える
コーチングは、地図の見方をいっしょに学びながら、目的地を目指すようなものです。
「今、実際にはどんな建物が見えていますか。山はどっちのほうですか?」
「地図の中で山の記号はこういうものです、どこにありますか?そうすると、今の位置はどこですか。どっちを向いているかがわかりますか?」
「目的地はどこですか?」
「どういう道を通っていけばいいか、見当がつきますか?」
「行こうとしている道の中で、こういう記号は通行止め、一方通行とかです。そういう箇所はないですか?」
コーチングはプロセスを大切にする
結果だけを求めれば、タクシーを拾ったり、道を尋ねるのが一番早いでしょう。でも、コーチングは結果だけを重視しません。むしろ、プロセスを大事にします。
気づいたり、学んだり、それによってこの経験が将来に生きてきます。これからも未知の難題に直面することがしばしばでしょう。そのときに、自分自身で解決に向かう力が養われていることは、とても大切なことです。コーチングは、ミッション・ワーカーがまさにその力を身につける助けとなります。
コーチングによって得られるメリット
では、具体的にミッション・ワーカーはコーチングによって何を得ることができるのでしょうか。
コーチングでは、コーチの問いかけに対して、クライアントは自分のことばで答えを見つけていきます。コーチはその答えを受け止めつつ、さらに深堀りしたり、必要なフィードバックを返します。その繰り返しの中で、クライアントは自分の位置を確かめ、新たな歩みを見出し、一歩ずつ前進していきます。
一般的に得られる数々のメリット
一般的に、コーチングで得られるのは、以下のような結果です。
- 自分がすべきことがわからなかった人が、使命を明確に自覚することができる
- どこから手をつけ始めていいかわからなかった人が、自分で計画を立てることができる
- 努力はしているけれど結果が出ない人が、自分に足りない点を理解し、克服することができる
- 計画を立てても実行に移せない人が、長く続けられる仕組みと動機づけを発見することができる
- 考えがまとまらず、人の協力を得ることが難しかった人が、明確なビジョンを見出し、効果的に伝達することができる
- 自分では伝えているつもりなのに、周囲には伝わっていない人が、円滑なコミュニケーション・スキルを身につけることができる
- 日常的にやることに追われていて、本当にすべきことがやっつけ仕事になっている人が、優先順位を決めて、スケジューリングできるようになる
- 指示待ちで人から言われてからしか動けなかった人が、率先して自分の果たすべき役割を見つけられるようになる
使命が明確になること
このようなコーチングの効果の中でも、特にミッション・ワーカーの助けになるのは、どのようなことでしょうか。
ひとつは、使命が明確になることです。すでにミッション・ワーカーは課題に取り組んでいるので、使命が明確なはずです。それでも、現実的な対応をする中で、妥協を重ねたり、軸がぶれたりすることは少なくありません。最初の志や熱意が失われて、取り組み自体が目的になってしまうこともあります。
そのようなとき、コーチの問いかけに答えながら、最初の志、それを胸に抱いたときの経験、熱い思いが蘇ってくることがあります。初心に帰る経験です。新しい力を得ることができます。
自己成長が促されること
もう一つは、自己成長への取り組みが促されることです。コーチとの対話の中で、目指すべき理想と現在地が明確になります。ではどうしたらよいか?と自ら問い始めます。
ともすれば状況のせいにしたり、他人の責任にしたりしてしまいがちです。仕方がない、なにをやっても同じ、と冷めた感情を持ちやすいものです。
しかし、コーチングでは、自分自身が何をどのようにすべきかが問われます。主体的、能動的に、どう取り組むのか、答えを見つけなくてはいけません。結果として、ミッションワーカーは自分が成長し、影響力を増していくことに注力するようになります。
精神的な同伴者を得ること
さらに、これが一番大きなメリットだといわれるのが、精神的な同伴者を得ることです。ミッション・ワーカーにとって、自分の使命を理解し、取り組みを応援してくれる存在を得ることは、なによりも心強く、取り組みを安定させます。
利害関係のない第三者だからこそ、自分の葛藤や不安を打ち明けることができます。良いとか、悪いとかの判断をしないで、そのまま受け止めてもらえます。これが思いの外、大きな安心につながります。
また、現実的な取り組みを定め、コーチに対して宣言することで、いい意味で強制力が働くようになります。自分の心の中で決めただけで、実際には何の行動にも結びつかず、なし崩しになってしまうことは、もうありません。
コーチングがもたらす結果
そのようなコーチングを受けることによって、ミッション・ワーカーの取り組みに、どのような結果がもたらされるでしょうか。また、ミッション・ワーカー自身はどのように成長するのでしょうか。
より効果的な、息の長い取り組み
コーチングによって、ミッション・ワーカーの取り組みそのものが、効果的なものになります。ミッション・ワーカーがベストの状態で取り組み、フルで能力を発揮するからです。もちろん、コーチがいればすべての夢物語が実現する、ということはありません。メジャーリーガーはメジャーリーガーなりに、草野球選手は草野球選手なりに、その人自身の最大限のの結果がもたらされます。
しかも、あまり意識されないことですが、長く取り組みが続くという効果があります。ドラマの一場面だけを見れば、ヒロインの涙だけが印象に残るかもしれません。しかし、大きなストーリーを意識するならば、その涙が笑顔に変わる展開を期待することもできます。ミッション・ワーカーの取り組みは、一朝一夕で結果の出るものではありません。マラソンのような持久力を要するものです。コーチングによって、モチベーションを健全に維持することができます。その結果、地道で、忍耐力を要する取り組みを長期間にわたって持続することができます。
ミッション・ワーカーの成長
さらに、目に見える取り組みの効果以上に、ミッション・ワーカー自身の成長がもたらされます。時間や金銭の使い方、人間関係の持ち方など、自己管理ができるようになります。自分自身で気がついている行動や思考のクセ、スキルアップの課題に取り組みます。また、コーチや周囲からのフィードバックをとおして、自分でも気がついていない課題に取り組むことも可能になります。
そのような中で、周囲からの信頼が増すでしょう。尊敬されるようにもなります。結果的に、ますます影響力を持つようになり、協力者の輪も広がります。ひいては、与えられた使命をさらに高次元、大きな規模で果たしていくことにもつながります。
このことは、人格的な成長を遂げたら働きが発展する、単純な話しではありません。今までの私の経験から言うと、コーチをつけて取り組み始めた、ということだけでも、周囲がその人を見る目が変わります。その誠実な取り組みの様子を見て、人々の信頼が深まり、尊敬を得られることでしょう。
ここまで、なぜミッション・ワーカーにコーチングが必要なのか、その理由と効果について説明してきました。十分に理解することができたでしょうか。
サーバント・スタイルでは、ミッション・ワーカーに対するコーチングを提供しています。2020年1月限定でコーチングのモニターを募集中です。詳しくは募集案内をご覧になり、気軽にお問い合わせください。
 ミッション・ワーカーの直面する多くの課題は、コーチングを受けながら取り組むことで、効果的に解決することができ、自己成長にもつながります。
ミッション・ワーカーの直面する多くの課題は、コーチングを受けながら取り組むことで、効果的に解決することができ、自己成長にもつながります。
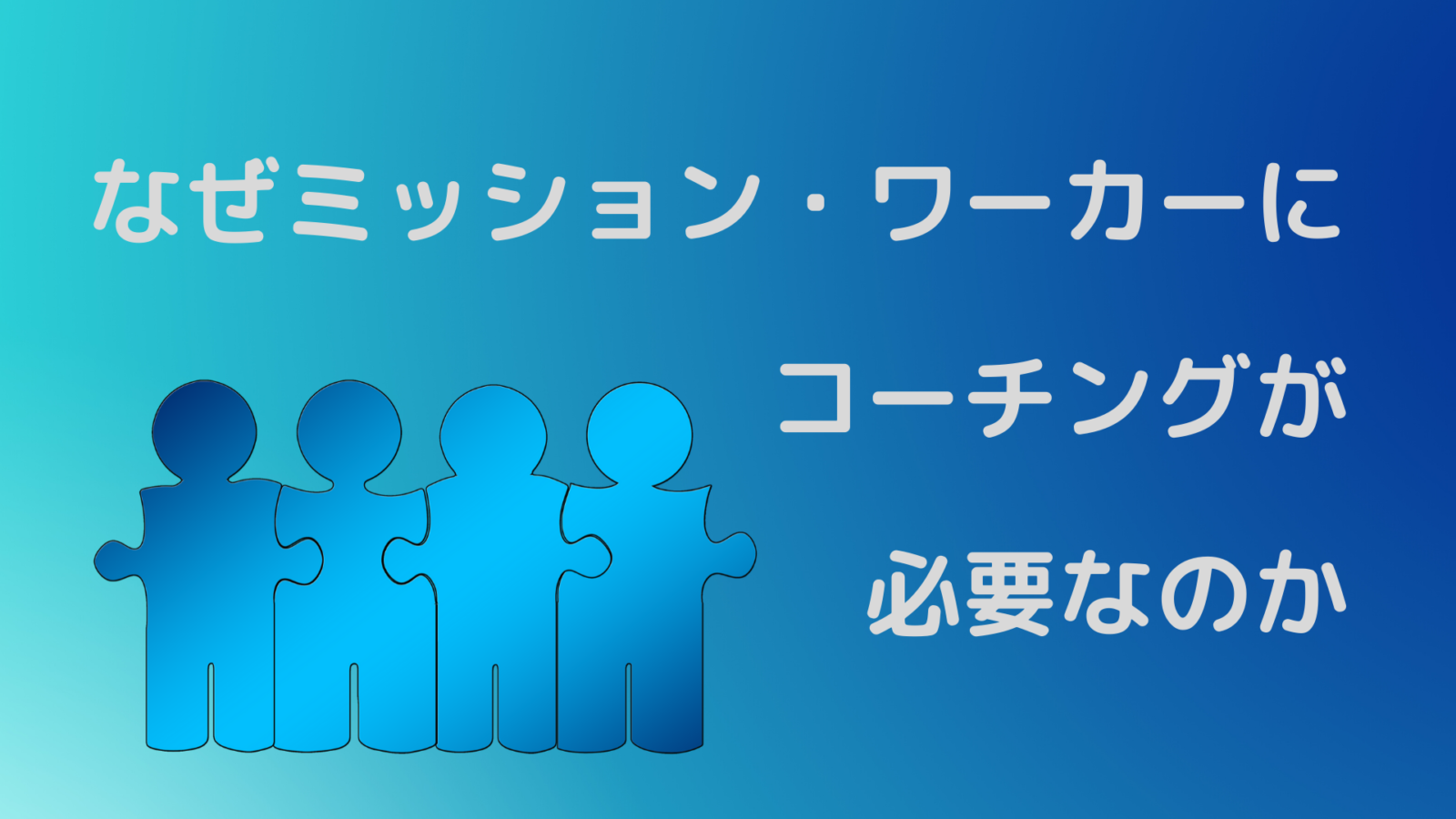
コメントを残す