サーバント・リーダーシップとは何かを説明しましたが、実際はどのような事例があるのだろうか、知りたいと思われることでしょう。
日本国内でサーバント・リーダーシップの事例として真っ先に挙げられるのが、池田守男による資生堂の経営改革です。
資生堂が直面した経営危機
資生堂は、化粧品業界の最大手とされ、売上は2位以下を倍近く上回っています。そんな資生堂ですが、今までに何度か、その座を失いかねないほどの経営危機に直面してきました。
その一つが、90年代の終わり頃でした。それまで大量に生産し、小売店を中心にセールスを仕掛け、大量消費の手段に訴えてきました。本部の戦略を半ば押し付けに近い形で小売店に強制してきたのです。しかし、もうその方法では思ったように小売店での販売が伸びない、という状況が生じます。加えて、97年の再販制度改革も向かい風になります。海外発の安い化粧品ブランド、インターネットでの通信販売なども台頭しつつありました。
このまま王座にあぐらをかいていたのでは、歴史上の王朝が時代に対応できずに滅びていったように、資生堂の看板も地に落ちることになってしまいます。
秘書から社長になった改革の旗手
改革の必要性に迫られた資生堂で、この時期に代表取締役になったのが、池田守男でした。
池田守男は1936年12月25日香川県生まれ。1961年に資生堂に入社し、取締役秘書室に配置されると歴代5人の社長たちのためにサポート役を果たしてきました。
そんな池田守男に、当時会長であった福原義春、代表取締役だった弦間明から声がかかり、大規模な経営改革の旗手を担う代表取締役への就任打診がありました。
奉仕と献身の精神で
池田守男は、若いときからキリスト教の信仰を持っており、大学は東京神学大学の神学部を卒業しています。いわゆる神学校と呼ばれる、牧師養成の意味合いの強い大学でした。熱心なクリスチャンであった池田守男は、個人的な信条として「奉仕と献身」を掲げていました。どこにおいても、自分ができる精一杯の奉仕をとおして、神の栄光を表そうと考えていたのです。
そのような中で、池田守男は代表取締役への就任を、神が自分に与えた天命だと受け止めます。聖書の一節「一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが、死ねば、多くの実を結ぶ」を心に刻み、自分がこのひと粒の麦となることを決意したのでした。神が自分に与えた使命を果たし、資生堂をよりよい企業にしていくために励むようになりました。
資生堂の基本理念に立って
池田守男がまずはじめに手掛けたのは、資生堂の経営とはいったいどのようなものであるべきか、という問いに答えを出すことでした。具体的な改革に先立ち、何を目指して改革を進めるべきかを明確にしたのです。
初心に帰り、資生堂の創業の精神に立ち返ります。中国の易経の一節「至哉坤元、万物資生」に由来し、大地の大いなる力から、すべてのよきものを生じさせ、もたらすという基本精神です。
それは他ならぬ、お客様と社会のためである、と明確に定義します。「天地のあらゆるものを融合させ、新しい価値を創造してお客様や社会に貢献する」という崇高な目的をあらためて確認しました。
逆ピラミッドの組織づくり
資生堂の経営改革はサーバント・リーダーシップによってなされた、と言われています。それは、どのようなことなのでしょうか。
サーバントの経営精神
池田守男には、モットーとする経営精神がありました。商いとは先義後利であって、自分たちの売りたいものを押し付けていてはいけないのだ、と考えていました。三方よし、つまり買ってよし、売ってよし、世にもよしという関係を構築すべきだという信念もありました。イエス・キリストのことばである「受くるよりも与えるが幸いなり」も、明確な行動指針でした。
こういった経営精神に基づいて、打ち出された改革案の骨子は「店頭基点の経営改革」でした。何よりもお客様と関わる小売店の店頭を大切にし、そのサポートのためにこそすべての経営はなされ、組織は奉仕するべきである、と打ち出したのです。
逆ピラミッド型の経営組織
店頭がすべてのことの基点であり、そのために自らはとことん仕える者であろう、と池田守男は考えていました。
その考えは、あるとき逆ピラミッド型の組織という形に行き着きます。部屋に戻ってきたとき、机の上に置かれていた組織図が目に入りました。いつも見ている方向からではない、逆さまの図を見たときに、これこそふさわしい組織の形だとひらめいたというのです。
お客様と関わる店頭こそが一番上であり、それを担当者が、支社が、本社が、そして最後には代表取締役である自らが下になって支援することが、資生堂のあるべき姿だと公表するようになりました。
まだこのとき池田守男自身はサーバント・リーダーシップという言葉を知らなかったようです。しかし、改革の内容は、まさにサーバント・リーダーシップの定着による経営の実践を目指すものでした。
サーバント・リーダーシップによって
では、奉仕と献身の精神に基づいて、具体的にはどのような改革がなされていったのでしょうか。
POSの導入
一つは、POS(販売時点情報管理システム)を小売店に導入したことです。これによって、一つ一つの小売店の特徴、ニーズが明らかになりました。
それまで、本部の商品戦略をすべての小売店に一律に課していました。それぞれの小売店の個性や特徴などは無視されたままでした。
しかし、POSが導入された結果、小売店に対する個別対応が可能になり、担当者はより親身になって小売店での販売支援をすることができるようになりました。
また、本部においても、個別の具体的なデータを見ながら、消費者のニーズ、目線から商品開発に取り組むようになりました。
ブランドの絞り込み
もう一つは、100以上あったブランドのラインナップを30以下に絞り込んだことです。これによって、店頭での接客を変えることができました。
というのは、100以上もブランドがあっても、小売店がそれをすべて適切に理解し、お客さんにおすすめすることは、事実上不可能でした。その結果、本部のセールス資料を受け売りするだけになってしまいがちでした。
しかし、POSのデータをもとに、消費者の真のニーズを理解し、ブランドの絞り込みがなされました。その結果、小売店は一つ一つのブランドの特徴を深く理解するようになりました。一人一人のお客様に合わせて、自信を持ってピッタリの商品を勧められるようになりました。
コミュニケーションを重視
このような取り組みを支えたのは、風通しのよいコミュニケーションでした。池田守男は、その大切さを示すかのように、自らも小売店、担当者、責任者たちと接点を持ち、会議に顔を出し、その声に耳を傾けました。「BC プロジェクト X」 という意見交換会では、毎回、現場の声が届けられ、それについて真剣な検討が積み重ねられました。
これらのコミュニケーションは、ガス抜きのためだけではありません。必要であれば、具体的な改革につながっていきました。例えば、店頭の小売員たちの制服です。新たに採用した制服が、環境への配慮などを重視した結果、機能的でなく、接客がしにくいという声が上がりました。その後、すみやかに制服は改善され、環境への配慮がされた、しかも機能的なものになりました。
また、池田守男は、経営改革の精神を全社に行き渡らせることに力を注ぎました。というのは、店頭基点の経営改革は、これまでの考え方をあらためる、パラダイムシフトを要するものであったからです。会議の場でも繰り返し奉仕の精神が説かれ、「想い」というエッセーが全社に届けられていきました。こうして、資生堂の経営改革は、一人一人の主体的な取り組みを伴う、力あるものとなっていったのです。
継承されるサーバントの精神
池田守男は、2005年に取締役会長となります。その後も経営陣によって店頭基点の経営は継承されます。
2006年には店頭美容部員の営業ノルマを撤廃され、かわりに顧客満足度に基づく評価が導入されました。たくさん売ることから、お客さんに喜んで買ってもらうことに主眼が置かれています。
資生堂はその後、グローバル化を目指して取り組みを進めます。これは、古い体質のまま、世界に広がる販売を把握、コントロールしようとしていたら、決して実現しなかったことでしょう。広がりゆく販路のいずれにあっても、お客様第一主義という世界スタンダードを実現すべく、今でも経営努力が続けられています。
まとめ
あらためて資生堂の経営改革を振り返ってみると、2つの特徴を挙げることができます。
- 奉仕の精神をもったリーダーの影響力
奉仕の精神をもった池田守男というサーバント・リーダーが、店頭を重んじる改革を影響力をもって実行していった。このリーダーなくして、改革の実現もなかった。 - 具体的な改革と実績
精神だけでなく、実際の改革によって現場が重んじられた。結果を享受した社員の意識が変わり、当事者として意欲的に取り組むようになった。浸透した社風に誇りをもつようになった。
以上、サーバント・リーダーシップが発揮された事例として、資生堂の池田守男による経営改革の事例について紹介しました。
責任をもつリーダーが本気で取り組むならば、確かにその影響力によって組織は変わる、という良い事例です。
 池田守男は信条とする奉仕と献身の精神で、資生堂の店頭基点の経営改革を行いました。店頭でのお客様との関わりに主眼を置き、経営者も組織全体もそのために仕えるという、サーバント・リーダーシップの実現を目指した事例でした。
池田守男は信条とする奉仕と献身の精神で、資生堂の店頭基点の経営改革を行いました。店頭でのお客様との関わりに主眼を置き、経営者も組織全体もそのために仕えるという、サーバント・リーダーシップの実現を目指した事例でした。
あなたが、この事例紹介から学ぶことのできることはなんですか?
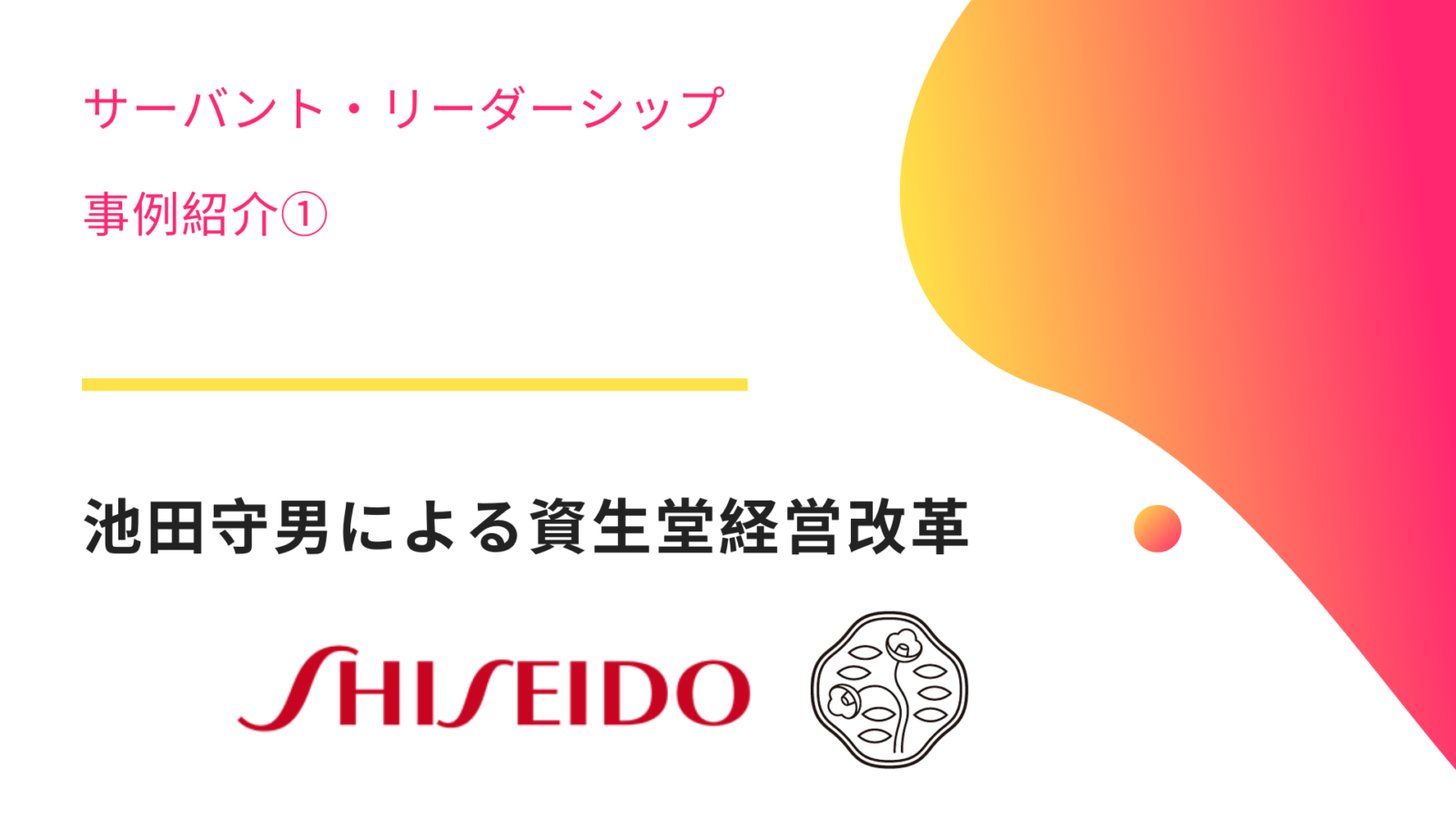
コメントを残す